ここでは、キミが書評を知るのに参考となる本をあげていく。これらの書き手はたんなる書評家ではなく、すぐれた批評眼をもつが、書評を書く上でもお手本にしたい。
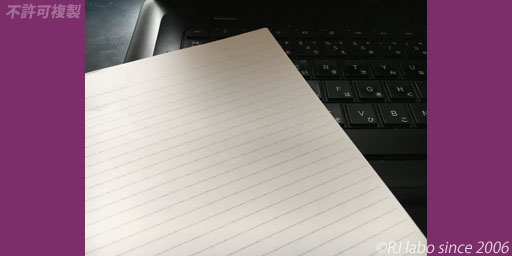
切り口、視点など、「そういう書き方もあるのか」と参考になるし、それらのトピック、要約、引用、コメントの各要素を意識して読めば、キミの文章力もアップするはずだ。
要約がすごい『ドン・キホーテ講義』
自分の中に明確なスタンスがあると、書評は書きやすい。自分の評価の押し売りはダメだが、作品に対する評価はあるのがあたりまえ。あとはそれをどう表現するかだ。
『ナボコフのドン・キホーテ講義』は『ロリータ』を書いた作家ナボコフが大学でおこなった講義をもとにしている。とてもぶ厚く、書評とはほど遠い本格評論である。
これをなぜ紹介したかというと、巻末についているオマケがすごい。あの膨大な『ドン・キホーテ』の要約である。これを読めば、要約にどれだけセンスがいるかよくわかる。
知名度バツグンでありながら、じっさいに読んだことのある人が少ないことでも有名な『ドン・キホーテ』を読みたくなる。そういう意味では書評の役割もはたしている。
言葉の魔術師ナボコフ
本題の講義の方も各回ごとに切り口が設定してあり、なるほど小説というのは、こういう風に読むものかと勉強になる。書評より批評が書きたい人はなおさら目を通すといい。
「言葉の魔術師」と呼ばれるナボコフの文体にも着目しよう。と言っておきながら、現在、この本は入手しにくい。そこで、『ナボコフのロシア文学講義 下』も挙げておく。
こちらは『アンナ・カレーニナ』の講義が載っている(この長大な小説の魅力を『ドン・キホーテ講義』では「捲き毛の美しさ」のひとことで語っているのがナボコフ流)。
この世界的名作は、ストーリーだけ読むと通俗だ。言い換えると、要約だけでは伝わらないなにかがあるわけで、そのなにかこそが「文学」と呼ばれる部分だろう。
双葉十三郎『ぼくの採点表』
次に紹介する双葉十三郎『ぼくの採点表』は映画評だ。1940~50年代の作品を収めた第1巻は3段組みで1000ページ弱。1850本の作品が載っている。
全5巻+別巻で戦前から90年代までカバーする。正統的な批評家と呼ばれるには、これだけの量と質に裏打ちされていないといけない、と知るためだけでも読む価値がある。
収録されている短評は、外国映画の公開時にリアルタイムで書かれた紹介文でありながら、批評としても一流だ。作品を☆の数で評価する元祖と言っていい。
その評価基準は「完成度」で一貫している。世間での評価や興行成績などは関係ない。その上、作品ごとに監督、俳優が記されていて、本にまとまると、辞書がわりに使える。
双葉評が楽しいのは、作品の評価が正確な上に、自分の好みもちゃんと入れ込んで、当時の映画批評家が見もしなかったようなB級映画の魅力まで伝えていることだ。
作品をカットごとに具体的に分析していく手法は、キミが書評/映画評を書くときの参考になる。具体的な内容を読んで興味をもった人がその映画を見ればいいという姿勢だ。
書評の方がおもしろい小林信彦
『ぼくの採点表』第1巻に序文を寄せている小林信彦は『ヒッチコック・マガジン』の編集長をするかたわら、書評をしていた。これに『ぼくの採点表』方式を採用している。
つまり、すでにある形式を自分の得意分野にあてはめたわけだ。まだ出版点数が少なかった当時の翻訳ミステリを毎月全巻読んで、買うべきかどうかを示したレビューである。
ネタバラシのできないミステリをどう紹介するかというテクニックの数々は大いに参考になる。ユーモア・ミステリなら、ジョークの方を紹介するなどがその一例だ。
翻訳ミステリの黎明期ゆえ、誤訳の指摘もたびたびあるが、あげつらうのではなく、善後策をきちんと示しているあたりが、さすがプロという感じで、見習いたい。
名作にツッコミを入れる斎藤美奈子
70年代まで書評はこう考えられていた。
「『面白い』というのは感想であり、評語ではない」
「書評には感想を書くものではない」
それがいまや世の書評は「面白い」のバーゲンセールのごとき様相を呈している。それらと一世を画す書評をしたければ、他人とちがった視点や切り口で勝負することだ。
斎藤美奈子は『妊娠小説』が認められ、文芸評論家としてデビューした。「恋愛小説」があるなら、「妊娠小説」があってもいいだろう、と勝手にジャンルを作ってしまった。
そうしておいて、有名な小説で、妊娠がどのように描かれているか、かたっぱしから論じている。この描き方、主人公(=男)の態度はないんじゃないかと。
発表後に「文学はそんな風に読むもんじゃない」と言う人があったらしいが、どんな世界も、新人は正統より異端で切り込んでいく方が早い。
内容的にフェミニズムの影響を受けているが、文中では「女の立場から言わせてもらうとねぇー」ぐらいのニュアンスだ。特定の思想や主義出張に踏み込むと、読者は離れる。
とりあげる本の基準を示した北上次郎
北上次郎が『作家の履歴書』の解説として「書評家が新刊書評をとりあげる本の基準」について寄稿した。この中で、「完成度は求めない」と述べている。
会話やキャラクター造形、描写などにひとつでも「はっとする」「おやっと思う」「新鮮な」ものがあれば、1500円ぐらいの元は取れる、ストーリーはどうでもいい、と。
彼が椎名誠と『本の雑誌』を立ち上げたのは1976年。当時の風潮に疑問を感じ、本の商品としての側面を語りたくてはじめたそうだ。まさに商品レビューである。
この精神がのちの営業スタッフに継承され、本屋大賞に結実した。創刊号は定価100円で500部だったという話は、なにか新しいことをやりたい人に勇気をあたえる。
【関連記事】
kindle unlimitedの読み放題がお得!覚えておきたい賢い利用法3選
サブスク初心者は人気の高いAmazon Primeを申し込むのがいい理由
