エッセイに書くことがないと思ったら
世の中には、エッセイを書くのが得意な人と苦手な人がいる。じつは、この両者の悩んでいることが、けっきょくのところ、いっしょだというのを知っているだろうか。
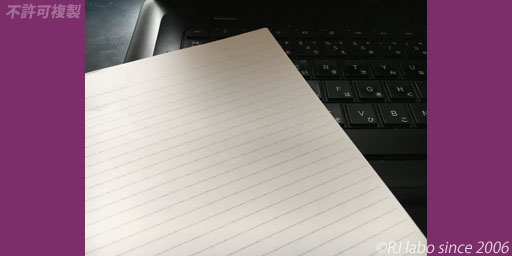
つまり、エッセイを書くすべての人の悩みは共通なのだ。少なくとも、その半分は重なり合っているとみて、まちがいない。本書では、その悩みを切り抜ける方法を教える。
ネタさえ思いつけばエッセイは書ける
本書の内容は、どんなエッセイにも応用のきくものではあるが、1000~1200字程度のエッセイをイメージしている。基本的な分量だが、これに苦労する人が大勢いる。
エッセイが苦手な人の悩みの代表は「書くことがない」「なにを書いていいかわからない」だ。ネタさえ思いつけば、文章はヘタでも、いちおう書き上げることはできる。
では、自分でエッセイが得意だと思っている人の悩みはなんだろう。端的に言うと、もっとうまくなりたいということだ。では、うまいエッセイとは、どういうエッセイか。
こまかい基準はべつとして、エッセイのうまさは次の2つに大別される。
(1)発想力が豊か
(2)表現力が豊か
エッセイは発想力が勝負
「発想力」というと、フィクションの基準のように思えるかもしれないが、そんなことはない。あるテーマ(お題)に対し、他の人にはない視点で書くといったうまさだ。
一般に、文章力といった場合は、「表現力」やそれ以前の基礎力をさしていることが多いが、読者の感想や評価は「発想力」によるところが大きい。
たとえば、死んだペットのことを書いた泣かせるエッセイがあるとする。この場合、泣かされる理由の大半は「どのシーンを取り上げるか」という発想力に関する部分だ。
「シーンを巧みに再現する」といった表現力もあるにこしたことはないが、表現力が未熟でもポイントを押さえていれば、泣かせることはできる。
テーマで書き出しが決まる
エッセイを書くにあたっては、なにを書くか(つまり、テーマ)が重要になる。そして、なにを書くか決めることは、書き出しを決めることに等しい。
文章において、書き出しが大切ということはよく言われる。読者を引き込むのが書き出しの役割だからだ。書き出しは、これから書こうとしている内容によって決まる。
エッセイは切り口が大事
たまにカンちがいしている人がいて、工夫した(悪く言えば、ヘンテコな)書き出しに情熱を傾けているが、内容と無関係の奇をてらった書き出しなんて意味がない。
うまい書き出しのひとつに「意外性のある書き出し」というのがあるが、これはテーマの扱い方に意外性があるから、結果として、書き出しに意外性が生まれるのである。
エッセイを書くときに大事なのは、まず、テーマだ。このテーマは、他人からあたえられる場合と、自分で決められる場合がある。いずれにせよ、大事なのは切り口だ。
自分でテーマを決める場合は、「なに」について書こうか悩むわけだが、それとて、けっきょくは、なに(主題)をどう書くか決めるわけだから、切り口の問題となる。
エッセイの書き手にとってテーマとは
逆に言うと、切り口さえ決まれば、主題はなんでもいい。目のまえに「消しゴム」があるから「消しゴム」について書こう! でいいのである。
では、「消しゴム」について書くとして、どう話をころがしていこうかと考える。なにを書いていいかわからないと悩む人は、じつは「どう書いていいのかわからない」のだ。
他人からテーマをあたえられた(○○について書け、と命じられた)場合も、それについて、どう書こうかと頭を悩ませることになる。「どう」というのが切り口だ。
エッセイを書く立場で言うと、テーマとは、これから書こうとする文章の主題と切り口までを含んだものである。論文で言うところのシーセス(目標規定文)と思っていい。
最も単純なエッセイの構成
シーセスというのは、簡単に言えば、「いまから、こういう内容について書こうと思っている」という意思表示で、エッセイでは(論文でも)文章の冒頭にもってくるといい。
構成について詳述はしないが、シーセスではじめて切り口を示し、クライマックスにあたる部分にいちばんキモとなる内容(大ネタ)をもってくるという展開が基本だ。
エッセイの切り口を見つけるコツ
切り口をさがすには、対象となるモノ(主題)から連想するものをどんどん挙げていき、これなら書けそうだ、という切り口を見つける。連想が苦手なら、辞書的定義でいい。
「消しゴムは文字を消すための道具である」
じっさいの辞書の説明とは、ちがってていい。ひとまず、こう書いてみて、そこから思いつくことを拾い上げる。
いや、文字だけじゃなく、絵や汚れを消すこともあるな、なんて気がついたら、それが切り口となって、文章がころがっていくかもしれない。
切り口さがしにはコツがある。
(1)主題から連想する言葉を挙げる
(2)動詞を見つけて文章化する
(3)つけ合わせを考える
エッセイは自分の体験を土台に書く
エッセイの大原則は、自分の体験(少なくとも、見聞したこと)を土台に書くことだ。体験はネタふり(起承転結の承)に使う場合と、大ネタ(転)にする場合がある。
自分の体験なら、なにか書くことはあるはずだから、主題から連想する言葉のうちで、自分の想い出と結びつくものをさがす。想い出が語れるようなテーマを設定する。
昔、消しゴムでハンコを作った想い出があれば、消しゴム版画で有名なコラムニストの話をつけ合わせにして、「遊びも極めれば仕事になる」(結)というエッセイが書ける。
動詞を見つけるとは、どういうことか。主題はたいてい名詞(消しゴム)であるから、それと対になる動詞(彫れる)をさがす。英文法で言うところのBe動詞は含まない。
動詞を使うと話が広がる
言葉には、話が広がりやすい(いわばエネルギーを含んだ)言葉とそうでない言葉がある。広がる代表が動詞で、主題に動きをもたせると、ネタが浮かびやすくなる。
「消しゴム」が主題なら、「消す」「消せる」といっただれでも思いつく動詞でかまわない。テーマはありきたりでも、ネタがおもしろければ、エッセイは成立する。
Be動詞にご用心
一方、Be動詞は、日本語だと「だ・である」「です・ます」となって名詞と名詞(あるいは、形容詞など)を結びつけるイコール(=)の役割しかなく、話がふくらまない。
モノが主題の場合にBe動詞を使うと、色や形など属性の話になりがちだ。「消しゴム」だと「白い」とか「四角い」とか。それに対比させるものって言ったら、豆腐?
それだと、豆腐とまちがえて、消しゴムを食ったみたいなエピソードがないと、エッセイにならない。言い換えると、「白い」「四角い」では話が広がらない。
もちろん、消しゴムったって、白以外の色もあれば、四角以外の形もある。そこに気づけば、なにかしらネタをひっぱってこれるかもしれないが、思いつくのに時間がかかる。
感情が動けば語りたいことが出てくる
それだったら、「文房具屋には、色とりどりの消しゴムが置かれている」と書いた方がイメージもふくらみやすい。「置かれている」という動詞にエネルギーがあるからだ。
昔、祖母に連れられた行ったときの記憶がよみがえるかもしれないし、文房具好きなら店に入ったときのわくわくした気持ちを思い出すかもしれない。
エネルギーのある動詞をもってくることで、キミの感情が動く。感情が動けば、「祖母」というつけ合わせや「語りたいこと」がわき出てくる。
それは「消す」といった消しゴムにとって、あたりまえの動詞でもそうだ。とくに「消せる」(消すことができる)なんて、可能性を含んだ動詞はエネルギーも高い。
インパクトのある書き出し
否定形にするこで、エネルギーが高まる動詞も多い。道具全般に応用できる動詞だと、「使う」がある。これを「使えない」「使わない」といった否定形にするわけだ。
あたえられたお題を否定するような書き出しは意表を突いて、かなりインパクトがある。自由テーマの題材でも、あえて使わないものをさがしてみるといいかもしれない。
例文:つづきが読みたくなる書き出し
たとえば、こんなエッセイの書き出し──
「私は消しゴムを使わない。消しゴムでいつでも消せると思うと、いい加減な気持ちで文章を書いてしまうような気がするからだ」
そのあと、なにを書けばこまったときは、つけ合わせを考える。「消しゴム」なら基本機能の「消す」をキーワードとして、「消す」で連想するものを対比させる。
「私が消しゴムを使わなくなったきっかけは(中略)
文字は消せても、過去は消せない。私がいい加減な気持ちで言ったひとことが彼女をあんなにも傷つけてしまうなんて……」
つけ合わせをもってきたときに、そちらの方がもとのテーマより大きくなることがあるが気にしなくていい。最初のテーマは、あくまでシーセス(目標規定文)にすぎない。
テーマとメッセージは分けて考える
エッセイの書き手にとってのテーマは、ゴールにたどりつく目安だ。国語の読解の授業などで出てくる「作者の言いたいこと」(メッセージ)ではない。
エッセイを書くには、最初にテーマを決め(言い換えれば、方向を定め)、その話をゴールまで運べば、じゅうぶんだ。メッセージや教訓はなくてもかまわない。
文章に苦手意識のある人はたいてい、「いいことを言わなきゃならない」というような先入観があって、自分で勝手に書くことをむずかしくしてしまっている。
いいことなんか言わなくても、つけ合わせをもってくれば、ほとんどの文章はまとまる。つけ合わせとは「自分以外の他人」であり、その人にまつわる想い出のことだ。
エッセイらしさを出すには
つけ合わせ、ということについて、もう少し考えてみよう。「つけ合わせ」という便宜上の用語は、主題に対する従の意味で、内容的には、こちらがキモになることもある。
つけ合わせは、自分の想い出に対比させる「他人の出てくるエピソード」が最良だが、エッセイの主題が他人の場合もあるだろう。その場合、どうすればいいのだろうか。
主題はできるだけ具体的に
まず、テーマの決め方から話そう。主題については、特定の個人にすること。エッセイを魅力にする鉄則は、できるだけ具体的に書くことだ。
たとえば、「父」というお題なら、「私の父」だ。結婚しているなら、「義父」でもかまわないが、抽象的哲学的な「父親とは」みたいな話にしてはいけない。
「友情」というお題なら、一般的な友情ではなく、特定の「友」の「情」について書く。それを文章化して、「Aは友情に厚い」といったテーマを設定する。
しかし、「友情に厚い」のままだとBe動詞だから、もう一歩踏み込んで、「AはBがこまっていたら、必ずたすける」のように、動詞を使って、友情のあり方を具体化する。
主題とつけ合わせを対比させる
この段取りは、自分が直接知らない偉人や有名人を主題にする場合も同様だ。
「○○選手はすごい」
ではなく、どうすごいのか具体的にする。
キミがその人物を「すごい」とか「やさしい」とか評価するには、その評価の土台となるエピソードがなにかあるだろう。「体調管理が常に万全だ」といったような。
なぜ、それをすごいと思ったかというと、自分はできていないからだ。つまり、つけ合わせで対比させるのはキミ自身(自分もがんばっているとプラスの対比でもいいが)。
第三者をつけ合わせにすることもできるが、他人を主題にしてホメる場合のつけ合わせは自分以外ない。「Aはすごいが、Bはすごくない」と書くのは、たんなる悪口である。
【関連記事】
読者の気持ちをつかむ地の文──文脈を意識して導入部を書く

